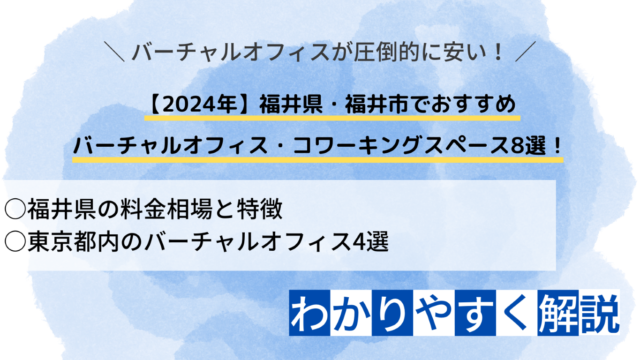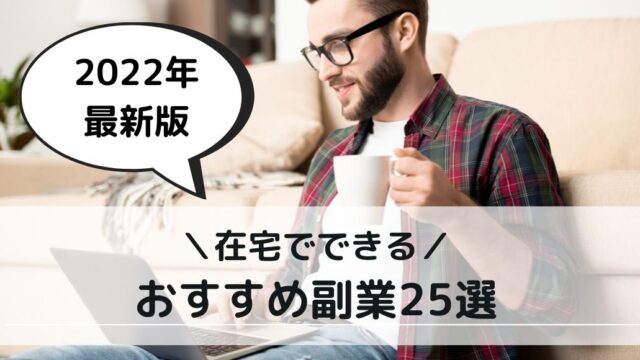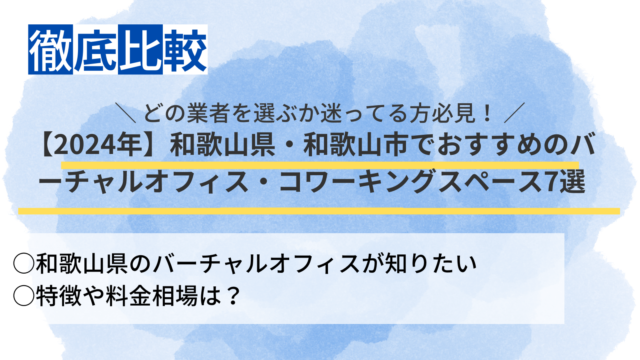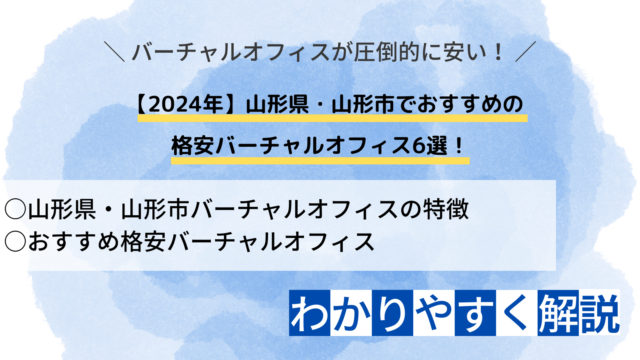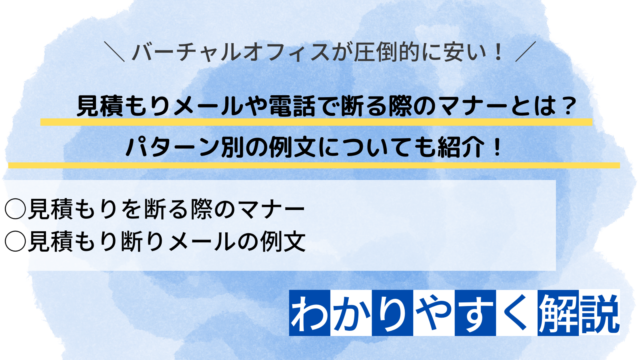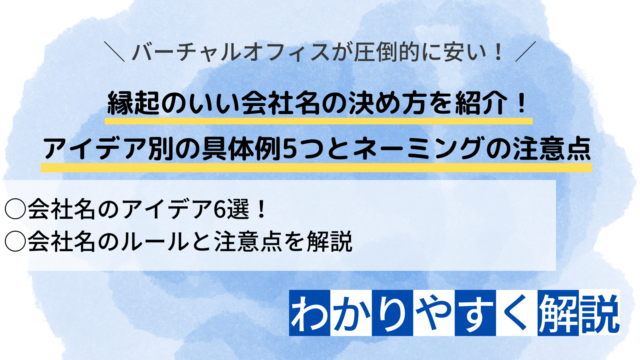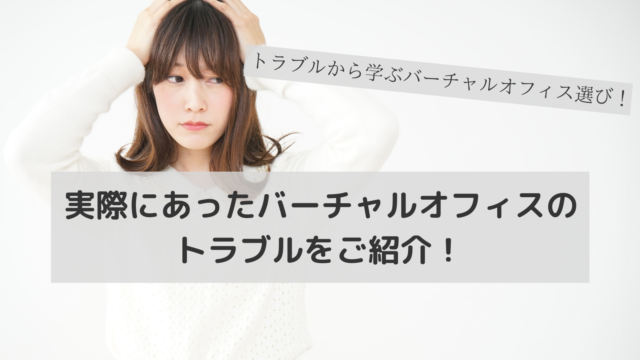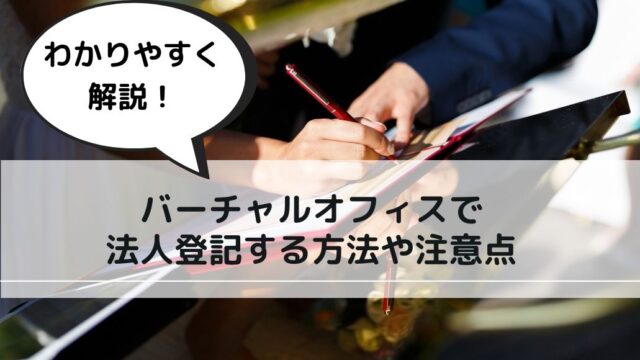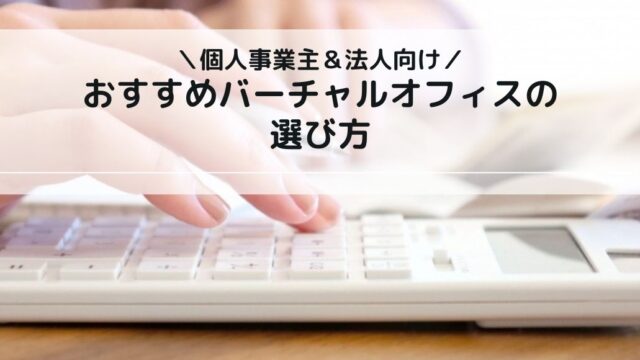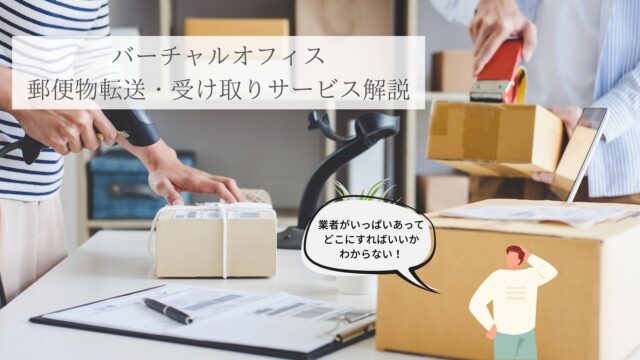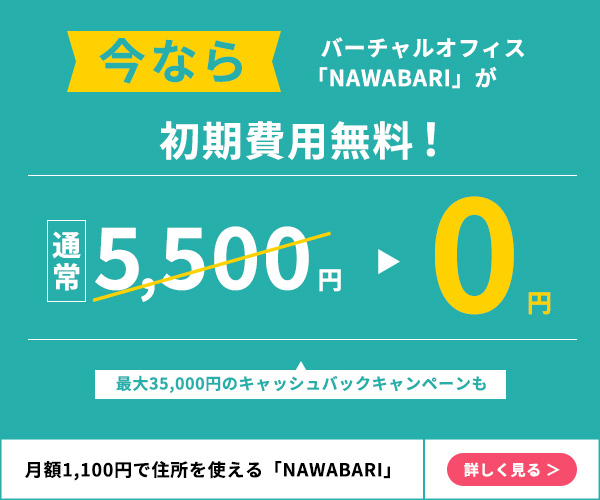バーチャルオフィスを利用して起業や副業を始める人が多くなっています。
バーチャルオフィスは、事業を始める時に欠かせない住所を手軽に借りられる便利なサービスです。
そのため、バーチャルオフィスの利用を検討している方、興味がある方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はそういった方へ向けて、バーチャルオフィスの経費計上について詳しく解説していきます。
バーチャルオフィスの費用は経費計上できる!
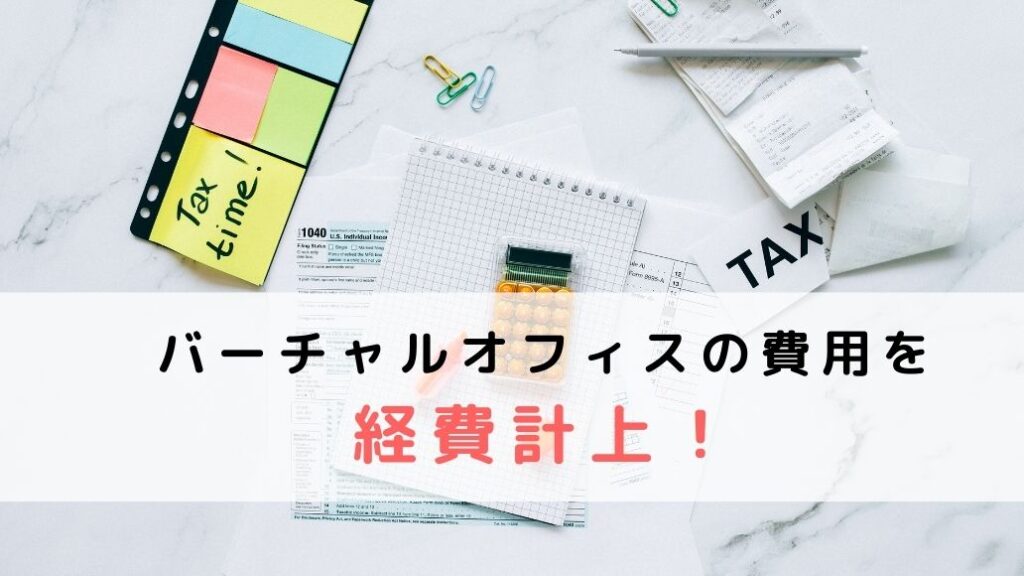
バーチャルオフィスは事業に必要な住所を手軽に借りられるサービスということで、起業する人や副業を始める人に人気となっています。
しかし、一般的なオフィスとは違って物理的なスペースを借りるわけではないため、利用料を経費として計上できないのではないかと考える人も多いです。
事業を行う上で必要な費用のことです
そのため、物理的なスペースを持たないバーチャルオフィスであっても、事業を営むために利用しているのであれば、利用料を経費として計上できます。
これは法人だけではなく、個人事業主であっても同じです。
バーチャルオフィスのメインのサービスだけではなく、郵便物の受け取り代行や電話転送サービスといった付随サービスの利用料金も事業用のものであればすべて経費計上できます。
バーチャルオフィスを経費にする場合に必要なもの

バーチャルオフィスの利用料を経費にする場合ですが、特別なものが必要になるわけではありません。
一般的な経費を計上する時と同じように、事業を営むために必要な費用として裏付ける証拠書類を用意しておけば問題ないでしょう。
代表的なものとしては、バーチャルオフィスの利用料の領収書や支払い明細などです。
中には経費にはならないと思っていたものが経費として計上できる場合もありますので、日頃から領収書などを保管しておく癖をつけておきましょう。
もし、領収書を失くしてしまった場合は、クレジットカード利用明細や出金伝票なども証拠書類として認められています。
クレジットカードで支払っているのであれば利用明細、銀行振込なら振込明細などを残しておきましょう。
出金伝票は自分で作成することができますが、あくまで現金が出ていった取引を記録するためのものです。
現金以外の取引に関しては利用できませんので注意しましょう。
毎月支払った金額を経費としてメモしておくことも大切です。
利用しているバーチャルオフィスのプラン内容が書かれた資料やホームページの情報などを控えておくのもおすすめです。
税務署のチェックが入った時に、説明がしやすくなります。
経費計上する際の勘定科目は「支払手数料」
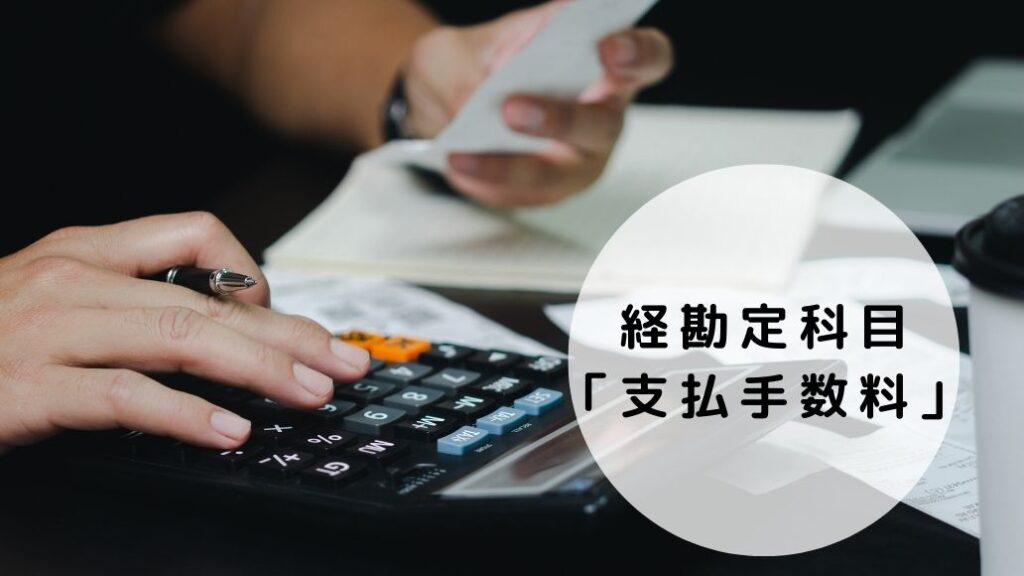
経費計上する際には勘定科目を選択する必要がありますが、バーチャルオフィスの利用料金は「支払手数料」として計上するのが一般的です。
支払手数料は事業取引で発生した費用を計上する際に用いられる勘定科目で、書類の申請に関わる事務手数料や銀行の振込手数料などにも用いられます。
バーチャルオフィスの利用料も事業取引で発生する費用となるため、「支払手数料」として計上すれば問題ありません。
バーチャルオフィスのオプション料金も経費になる
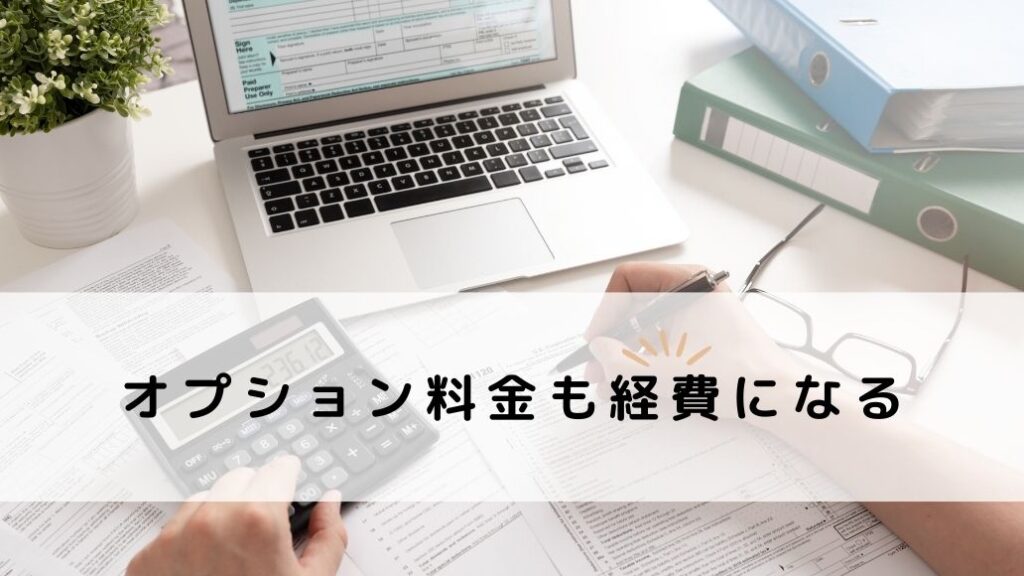
バーチャルオフィスには様々なオプションがついています。
人気となっているのが、郵便物転送サービスです。
こちらのサービスを利用すれば、バーチャルオフィスに届いた荷物を指定した住所まで転送してもらえます。
バーチャルオフィスは物理的なスペースを持っていないため、仕事は自宅など別の場所で行うケースが多いです。
その時、郵便転送サービスを利用していれば、わざわざバーチャルオフィスの住所まで荷物を取りに行く必要がありません。
会議室をレンタルできるバーチャルオフィスも多くあります。
取引先と打ち合わせをする時など、物理的なスペースが必要になった時に便利なサービスです。
他には秘書代行や記帳代行などのオプションを用意しているバーチャルオフィスもありますが、こういったオプション料金も経費として計上することができます。
バーチャルオフィスを経費計上する際に注意すること

自宅で仕事をしている人は仕訳の仕方が異なる
住所や電話番号はバーチャルオフィスのものを使用し、仕事自体は自宅で行うというケースも多いです。
その場合は仕訳の仕方が異なるため、注意が必要です。
個人事業主としてバーチャルオフィスを利用しながら自宅で仕事をする場合は、バーチャルオフィスの利用分だけではなく、自宅の光熱費や家賃などを家事按分することができます。
自宅で仕事をしていると、家賃などの支出がプライベート用と事業用で混ざることになります。
その時に、事業で使用した比率分は経費として計上できますが、これを家事按分と呼びます。
バーチャルオフィスの利用分は「支払手数料」となりますが、自宅の家賃や光熱費などは別の勘定科目で計上することになりますので注意しましょう。
家賃に関しては、
事業用部分を「地代家賃」
家事部分を「事業主貸」
として計上します。
電気代や水道代などの勘定科目は水道光熱費です。
家事按分の比率に関しては各々の判断に任せられますが、仕事でどの程度使っているかを客観的に見て判断する必要があります。
バーチャルオフィスは「賃借料」に該当しない
一般的なオフィスは土地や建物などのスペースを借りることになるため、賃借料として経費を計上することになります。
しかし、バーチャルオフィスはあくまで住所や電話番号など、オフィスに関する機能のみを貸し出しているサービスです。
そのため、基本的にバーチャルオフィスは賃借料に該当しません。
バーチャルオフィスを利用していたとしても、実際の事業を自宅などで行っている場合は、前述した通りに支払手数料として経費を計上するのが基本です。
バーチャルオフィスと似たようなサービスにレンタルオフィスやシェアオフィスなどがありますが、レンタルオフィスやシェアオフィスは実際にスペースを借りて利用することになるため、経費は賃貸料として計上することになります。
同じようなサービスに見えても、取り扱いは異なりますので注意しましょう。
勘定科目が「支払手数料」ではない場合もある
バーチャルオフィスの利用料は基本的に「支払手数料」として経費計上することになりますが、勘定科目の分類はケースによって変わります。
例えば、秘書代行や電話代行といったバーチャルオフィスの付随サービスに関しては、外注費として計上することも可能です。
もしバーチャルオフィスを利用した時に発行される請求書や領収書に、内訳が書かれている場合には勘定科目を細かく分類しても問題ありません。
郵便物転送や電話番号レンタルの利用料は「通信費」
会議室の利用料は「会議費」
秘書代行や記帳代行などの利用料は「外注費」
として分類されることが多いです。
しかし、勘定科目を細かく分類しても課税額は変わりません。
経費の内容を正確に把握しておきたい場合などに、細かく分類しておくとよいでしょう。
勘定科目をどのように分類するかは特に細かいルールが決められていません。
しかし、記帳に一貫性を持たせる必要があるため、一度分類したものはなるべく変更しないようにしましょう。
毎回勘定科目を変更してしまうと、どのような目的で使用した経費かを説明するのが難しくなってしまいます。
税務署から確認を受けてしまうこともありますので、分類がよく分からない場合は「支払手数料」や「外注費」としてまとめておく方が無難です。
まとめ
しっかりと経費計上しておくことは、節税のために重要なことです。
経費を正しく計上すれば、税額を低く抑えられます。
バーチャルオフィスの利用料も経費計上可能ですので、領収書などをしっかり保管しておきましょう。
色々なバーチャルオフィスがありますが、NAWABARIが人気になっています。
法人登記可能な住所の貸し出し、多くのプラットフォームへサービスを提供しているなど魅力的なサービスですので、ぜひ利用を検討してみましょう。